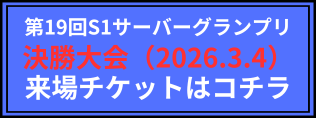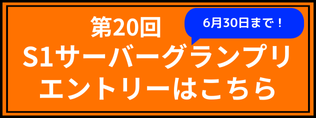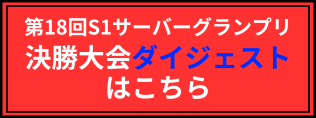[問 題]
以下の(ア)~(オ)について、手洗いのタイミングとして正しいものには〇を、間違えているものには×を選択しなさい。
(ア)トイレを使用した後(イ)調理場へ入る前
(ウ)汚れる可能性が高い作業の後(生の肉、魚を触る/使用済みの調理器具を触る/廃棄物を処理する・食事後の食器を片付けるなどの作業)
(エ)加熱工程のない食品に触れる前
(オ)盛りつけ作業の前
出典:厚生労働省_ノロウイルス等の食中毒防止のための適切な手洗い
※YouTube動画(音が出ます)
【公開問題2】
『衛生について/従業員罹患(りかん)時の対応』
近年の食中毒届出数は、年間1,000件程度、患者数は10,000人前後で推移しています。 また、食中毒事案のうち、ノロウイルスによるものは、国内で報告された食中毒件数の2割、患者数の5割を占めています。 ノロウイルスによる食中毒は、主に調理者を通じた食品の汚染により発生します。 飲食店にて、直接食品に触れる仕事をするスタッフがノロウイルスに感染した場合は、厚生労働省の「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいた対応が求められます。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中で、従業員がノロウイルスに感染した場合において、最も適切な対応を1つ選びなさい。
(ア)通常通り勤務を続ける。(イ)症状が軽い場合はマスクを着用して勤務する。
(ウ)医療機関を受診し、回復するまで出勤を控える。
(エ)店舗内でアルコール消毒を強化し、勤務を続ける。
(オ)食品の加熱調理を徹底すれば問題ない。
出典:厚生労働省_大量調理施設衛生管理マニュアル(8~9ページ)
【公開問題3】
『アレルギー症状』
食物アレルギーの症状は多彩で、人によって異なるほか、同じ人でも食べる量や体調によって症状が変わります。 特に、重篤な全身症状を「アナフィラキシー」といい、急速に進行して死に至ることもあるため、迅速な対応が求められます。[問 題]
次の(ア)~(オ)は、食物アレルギーで起こる代表的な症状ですが、この中で最も多い症状を1つ選びなさい。
(ア)じんましん、かゆみ、赤くなるなどの皮膚の症状(イ)のどが締めつけられる感じ、息苦しさなどの呼吸器の症状
(ウ)目の充血、まぶたの腫れ、口の中や舌の違和感などの粘膜の症状
(エ)腹痛、下痢、おう吐などの消化器の症状
(オ)ぐったりする、意識がもうろうとするなどの全身の症状
出典:東京都保健医療局_食品衛生の窓
【公開問題4】
『インバウンド対応/イスラム教徒対応』
近年、訪日外国人観光客の多様化が進む中で、イスラム教徒(ムスリム)の方々への配慮も飲食店にとって重要なテーマとなっています。ムスリムの方は宗教上の戒律により、ハラル(halal)とハラム(haram)の考えを守ります。 ハラル(halal)とは、イスラム教の教えにおいて「許されている(合法な)」という意味で、イスラム教徒が口にしてよい食べ物や飲み物、行動などを指します。ハラム(haram)とはその逆で、「禁じられている(違法な)」という意味があり、イスラム教徒の方のニーズを理解し、無意識のうちに宗教上の禁忌に触れないような対応が求められます。[問 題]
イスラム教徒の方への飲食店での対応として、以下の(ア)~(オ)の中で正しいものを1つ選びなさい。
(ア)ムスリムの方も旅行中は戒律を一切守らないため、気にしなくてよい。(イ)料理に豚肉を使用していなくても、同じ調理器具で他の豚肉料理を調理している事を望まないムスリムの方がいる事を理解しておく。
(ウ)基本的にムスリムは全員、お酒を飲みたいため、積極的に日本酒や日本ワインをおすすめすることが大切である。
(エ)料理のソースに赤ワインを使用している場合、ソースは食材に入らないため、何も説明せずに提供してもよい。
(オ)ベーコンは塩漬(えんせき)しているため、ハラル食材となり、何も説明せずに提供してよい。
出典:熊本市「ムスリム旅行者おもてなしガイド」
【公開問題5】
『基本的な英語接客表現』
訪日外国人観光客の増加に伴い、飲食店でも英語による簡単な接客が求められる場面が増えています。「いらっしゃいませ」や「こちらへどうぞ」「お会計は〇〇円です」など、基本的なフレーズを覚えておくことで、外国人客にも安心感を与えることができます。英語が苦手なスタッフでも、簡単な定型表現を使うだけで接客の質を高めることが可能です。[問 題]
次の(ア)~(オ)の接客用語の英訳のうち、間違えているものをひとつ選びなさい。
(ア)ご予約はされていますか? → Do you have a reservation?(イ)アレルギーはありますか? → Do you have any food allergies?
(ウ)苦手な食べ物はありますか? → Do you have anything you like?
(エ)お料理の追加はいかがですか? → Is there anything else you want to order?
(オ)美味しかったですか? → Did you like it?
出典:S1サーバーグランプリ 公式YouTubeチャンネル 「S1飲食店応援チャンネル」 ショート動画Let’s English より抜粋
【公開問題6】
『ハウスルール』
「ハウスルール」とは、それぞれの店舗で独自に定めているルールのことです。 ハウスルールがあることで、お店の秩序が保たれ、スタッフも気持ちよく働くことができます。 それによりスタッフのモチベーションも高まり、お店全体の雰囲気が良くなることで、お客様にも気持ちよく過ごしていただけるようになります。[問 題]
以下の(ア)〜(オ)のうち、ハウスルールに関する内容として不適切なものを1つ選びなさい。
(ア)お客様への対応に関して統一感を持たせたるなど、ミスやクレームを軽減するために、サービスに関するハウスルールを設けておくほうがよい。(イ)飲食店にとって衛生管理は非常に重要であるため、従業員の身だしなみや手洗い、清掃についての基準や方法を明らかにしておいたほうがよい。
(ウ)互いに気持ちのよい環境をつくり、職場の一体感を作るために、出勤時、退勤時、休憩に入るとき、休憩から戻るときなどにする統一した挨拶を決めておいたほうがよい。
(エ)ハウスルールは飲食店でしか使わない専門用語であるため、経験や知識がある従業員が活かせる内容でまとめておくほうがよい。
(オ)ハウスルールは飲食店未経験の新人従業員でも理解できるように、できるだけシンプルかつ平易な表現でまとめることがよい。
出典:Square_飲食店で役立つハウスルールとは?作成のポイントやメリットを紹介
【公開問題7】
『敬語の意義』
敬語とは、相手に対して敬意を示すための丁寧な言葉遣いのことです。 日本語では人との関係性や状況に応じて敬語を使い分けることが求められ、特にビジネスや接客の場面で重要な役割を果たします。[問 題]
飲食店での接客において、お客様に対して敬語を使うべき理由として最も適切なものを一つ選びなさい。
(ア)お客様に対して親しみやすさを示すため。(イ)お客様に対して敬意を示し、良好な関係を築くため。
(ウ)上司に対して使用する言葉なので、お客様に対しても同じように使う。
(エ)商品の価値を高めるためだけに使う。
(オ)何も理由はない。
出典:PHP人材開発
出典:文部科学省「文化審議会「敬語の指針」(答申)について」
【公開問題8】
『敬語/正しい使い方の確認』
サーバーの言葉遣いは、お客様が気持ちよく食事できるかどうかを大きく左右します。 例えば間違った料理を提供してしまった際、「すみません、間違えました」と言われるのと、「申し訳ございません。すぐにお取り替えいたしますので、少々お待ちいただけますか?」と言われるのでは、印象が全く異なります。 飲食店にとって適切な言葉遣いができているかは、気を付けるべき重要ポイントになります。[問 題]
敬語には5種類ありますが、次の(ア)~(オ)の中で、敬語の説明として不適切なものを1つ選びなさい。
(ア)相手の動作などを高めて、相手に敬意を示す敬語を『尊敬語』といいます。例:「いらっしゃる」「おっしゃる」など。(イ)自分の動作をへりくだって示す敬語を『謙譲語』といいます。例:「伺う」「申し上げる」など。
(ウ)丁寧さを表す敬語を『丁寧語』といいます。例:「です」「ます」「ございます」など。
(エ)特定の業界で使われる敬語を『専門語』といいます。例:「おあいそ」「お通し」など。
(オ)相手を軽んじる言葉を『卑下語』といいます。例:「うちの者」「つまらないもの」など。
出典:ぶけなび_あなたの店は大丈夫?接客用語の基本を確認して接客レベルを上げよう
【公開問題9】
『言葉遣い』
飲食店の接客では、正しい言葉遣いがお客様との信頼関係の構築に直結します。一方で、接客において誤用が定着している表現も少なくありません。サーバーがそのような表現を使うと、お客様が不満に思ったり、店のレベルが低く評価されてしまったりする要因になります。言葉はおもてなしの基本であり、一人ひとりの意識が店舗の「印象」を形づくると心得ましょう。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中で、→の右側の言葉遣いが適切に直されていないものを1つ選びなさい。
(ア)「こちらかつ丼になります」→「こちらかつ丼です」(イ)「でよろしかったでしょうか」→「でよろしいでしょうか」
(ウ)「ご注文の方は以上でよろしいでしょうか」→「ご注文は以上でよろしかったでしょうか」
(エ)「少々お待ちいただく形となるのですが、よろしいでしょうか」→「少々お待ちいただいてよろしいでしょうか」
(オ)会計時)「5,000円からお預かりします」→「5,000円、お預かりします」
出典:ぶけなび_あなたの店は大丈夫?接客用語の基本を確認して接客レベルを上げよう
【公開問題10】
『基本動作』
飲食店において、より顧客満足度を向上させるための接客の考えのひとつに[パーソナルスペース]の確保があります。 接客時のパーソナルスペースとは、お客様が快適に感じる他者との適切な距離のことを指します。距離の取り方によって接客の印象が大きく変わるため、適切なパーソナルスペースを保つことができる立ち位置が重要と言えます。[問 題]
接客時における適切な立ち位置として、次の(ア)~(オ)の中から間違えているものを1つ選びなさい。
(ア)お客様と75cm~120cmの距離を保ち、自然なコミュニケーションを心がける。(イ)斜め45度の位置に立ち、安心感を与えるようにする。
(ウ)正面に立ち、威圧感を持たせることで信頼関係を築く。
(エ)真横に立ち、親しみやすさを演出する。
(オ)アイコンタクトは適度に取るようにし、視線を合わせすぎると不快に感じることもあるため、適度なバランスを意識する。
出典:日本サービスマナー協会
【公開問題11】
『接客について/基本動作』
お客様満足度は「商品満足度」×「従業員接客満足度」の掛け算で決まると言われています。 飲食店における接客は営業時間が長時間にわたることも多く、従業員が無意識にとった行動が、お客様に不快感を与えることも少なくありません。常に気配りのある接客を心がけ、基本動作を意識することが求められます。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中で、お客様が不快に感じてしまう可能性が高い接客をすべて選びなさい。
(ア)ぼさぼさの髪・厚化粧・香水・爪や制服の汚れ等の不潔な服装、身だしなみ。(イ)お客様が言った言葉を訂正する (例)お客様:「お水をください」→従業員:「チェイサーをお持ちします」。
(ウ)特定の政党、宗教、球団を話題にする。
(エ)柱や壁に寄りかかる。
(オ)お見送りをせずに片付けを始めてしまう。
出典:静岡県飲食業生活衛生同業組合『飲食店新規従業員 – 接客マニュアル』
出典:「ユニシアコミュニケーションズ『飲食店の接客マニュアルに絶対載せるべき14の基本』」
【公開問題12】
『お客様属性』
飲食店において、顧客満足度を高めるためには、来店されるお客様の属性に応じた柔軟な接客対応が重要です。たとえば、高齢者には聞き取りやすい話し方、家族連れには子どもへの配慮、外国人には文化や習慣への理解が求められます。また、カップルやビジネス利用など、目的に応じた心配りもサービスの質を左右します。[問 題]
以下の(ア)〜(オ)のうち、お客様の属性に配慮して接客したつもりでも、かえって顧客満足度を下げてしまう可能性が高い対応を1つ選びなさい。
(ア)老年のお客様に対して、御注文の復唱の声をハキハキとゆっくり話すことで満足度向上を目指した。(イ)お子様を含むご家族から頂いた料理の注文のうち、お子様が召し上がる商品を先に提供した。
(ウ)接待でご来店いただいたお客様へのドリンクの提供は、ホスト役(幹事役)が頑張っていたから、ホスト役から提供した。
(エ)外国人のお客様が、お箸をうまく使えない様子であったので、フォークとナイフをご利用になるかを確認した。
(オ)カップルでご来店のお客様で、女性のお客様がお手洗いにお立ちになって姿が見えなくなった瞬間に、男性からこそっと「お会計をお願いします」と言われたので、女性がお手洗いから戻ってくるまでに速やかにお会計を終わらせた。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
【公開問題13】
『電話のマナー』
電話でのお客様への対応は、自分の表情が相手に見えないため、明るく聞きやすいトーンで電話口の相手へこちらが笑顔である事が伝わることが大切です。 電話対応はそのような声質が大切であるとともに、お客様とのやり取りや、要件を的確に把握し対応することがより重要です。[問 題]
電話でのお客様との対応について、次の(ア)~(オ)の中で、間違っている内容の文章を1つ選びなさい。
(ア)電話に出るときは「お電話ありがとうございます。〇〇(店名)担当〇〇がお受けいたします」等、お礼を述べて名乗るようにする。(イ)電話口の相手の年齢や状況を加味して、適度な声の大きさとスピードで、はっきりと話すことが重要です。特に混雑した店内では、バックグラウンドノイズがあるため、相手に確実に伝わるように意識する。
(ウ)ご予約情報などの用件をお客様に何度も確認しないように、メモを取りながら一回で聞き取るように心がける。
(エ)お客様が先に電話を切ったことを確認して電話を切る。
(オ)電話を切った後、電話で受けた予約内容に不安要素があっても、確認の電話をするとお客様には迷惑になるので、不安なままでいい。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
【公開問題14】
『予約システムの活用と顧客満足』
近年、飲食店ではホームページやSNSと連携させて予約システムを導入する店舗が増加しています。 これらのシステムは単なる業務効率化の手段にとどまらず、予約の利便性やパーソナルなサービス、スムーズなコミュニケーションなどを通して、お客様の満足度を高めるツールとして注目されています。 予約時点から来店・食事・退店後に至るまでの一連の体験において、安心感や特別感を演出できることが強みです。[問 題]
飲食店で予約システムを導入するメリットが、どのようにお客様の満足度に繋がるかという説明として、不適切なものを(ア)~(オ)の中から1つ選びなさい。
(ア)予約システムによって、スタッフは電話対応の手間が減り、来店されたお客様へのサービスに集中できます。これにより、お客様はよりきめ細やかなおもてなしを受けられ、お店での体験全体の満足度が向上します。(イ)お店の営業時間やスタッフの電話受付時間を気にせず、お客様の都合の良い時にいつでもどこからでも簡単に予約ができるため、営業中、お店に予約の問い合わせの電話が直接来た場合「予約システムでお願いします。」と会話を遮り、営業中の接客に集中することが望ましい。
(ウ)予約システムからの自動確認メールやリマインダー通知は、お客様に「ちゃんと予約できた」という安心感をもたらします。さらに、来店後には感謝のメッセージが届くことで、お客様は特別感を味わい、お店への良い印象が残り、次回の来店への期待へと繋がります。
(エ)お客様の来店履歴や好みがシステムに蓄積されることで、一人ひとりに合わせた特別なサービスを提供できます。お客様に「自分のことを覚えてくれている」と感じていただくことで、よりパーソナルで心温まる体験を提供し、満足度を高めます。
(オ)お客様自身が日時や人数、コースなどを直接システムに入力するため、お店とのやり取りで生じる伝え間違いや、予約の抜け漏れといったヒューマンエラーが大幅に減少します。これにより、お客様は自分の要望を確実に伝えることができ、イメージ通りの食事体験を実現できます。
出典:マネーフォワード
【公開問題15】
『ご案内時の接客シーン』
お客様が入店時に、お店や従業員に抱く印象は、良くも悪くも後に引きずると言われています。 逆に言えば、ご案内の印象が良いとお客様は心地よく食事を楽しむことができると考えられます。[問 題]
以下は、お客様のご来店~お席へのご案内までのシーンの文章です。以下の(ア)~(オ)のうち、より良い顧客満足度を提供するための心構えとして正しいものには〇を、そうではないものには×をつけなさい。
(ア)お客様の入店に気づいたら、すぐにそのお客様のもとに伺うことが理想であるが、すぐに伺えない場合は、「いらっしゃいませ」や「こんにちは/こんばんは」のお声掛けや、目を合わせての会釈などで、入店への認知をなるべく早く伝えることが望ましい。(イ)ご来店されたお客様の立ち振る舞いや服装、お連れ様がいる場合はその会話の仕方などから、ご来店目的やおおよその予算を想定することで、より良い接客サービスを提供できるようになる。
(ウ)ご予約のないお客様がご来店され、ご案内できるお席があるかどうか分からない場合は「すぐに確認して参ります」のようなお声掛けをし、なるべく早く空席状況を確認し、今現在満席でも20分後にご案内ができそうな場合は「満席です。」とお伝えするだけではなく「今は満席ですが20分お待ちいただければ、お席のご用意ができます。」と、お伝えすることが望ましい。
(エ)入口からお席にご案内する際は、「あちらのお席です」となんとなくの方面だけ指図し、お客様が先に歩き、その後ろをサーバーが付いていく流れが望ましい。
(オ)ベビーカーをお持ちのお客様や、車椅子の方、高齢のお客様には適切な席を案内するなど、状況に応じた気遣いが求められます。お客様の表情や動きから「何かお手伝いできますか?」と自然に声をかけるのも良い対応である。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
【公開問題16】
『オーダーテイク』
お客様からご注文を受ける「オーダーテイク」は、単に注文内容を聞き取るだけでなく、表情・声のトーン・提案力・確認作業など、様々な要素が求められます。適切なコミュニケーションを通じて、お客様が安心して注文できる雰囲気を作ることが、満足度向上につながります。[問 題]
以下の(ア)〜(オ)のうち、オーダーを受ける際の考えや行動としてふさわしくないものを1つ選びなさい。
(ア)笑顔を基本姿勢とし、相手の目を時々見ながらしっかりとオーダーを記入(打ち込み)し、最後に間違いがないかどうか、ハキハキとした声で復唱をして確認をする。(イ)お客様がわからないであろうお料理の量感(ポーション)を、相手の人数に合わせ伝えることによって、お客様の求める適正量へと導く。
(ウ)ご飯ものやデザート類は、後半に食べたいのか前半に食べたいのか、また白米であれば何かと一緒に食べたいのか等、お料理の順番やタイミングを伺う。
(エ)アレルギーが多い食材や、辛い調味料(わさび等)が含まれているかが、わかりづらい商品名の場合は、食材の説明を行う。
(オ)お客様から直接注文を受ける際は、常に下を向き目線を合わすことなく、なるべく無言で復唱はせずに対応する。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
【公開問題17】
『中間接客/テーブル状況やお客様心境の確認』
飲食店において、お客様がお食事をしている最中の「中間接客」は、ただ料理を出して終わりではなく、満足度を左右する重要なポイントです。 特にテーブル上の状態やお客様の心境に目を配ることは、お客様の居心地や快適さに直結します。 「気づいてくれて助かった。」「何も言わなくても整えてくれた。」と感じさせる対応は、無言のサービスとして高く評価され、リピーターづくりにもつながります。 スタッフが状況を見て適切に行動できるよう、確認すべき視点を持つことが求められます。[問 題]
下の(ア)~(オ)の中から、テーブル状況やお客様心境を確認する時に気を付けて見るべきところをすべて選びなさい。
(ア)食べ終わっている、もう下げてほしいと思われている食器、グラス類がないか。(イ)おしぼりが汚れていた場合、おしぼり交換の必要がないか。
(ウ)水やお茶などのサービスドリンクが減っていないか。
(エ)料理の提供が遅れていないか、不安そうな様子が見られないか。
(オ)料理を食べ進めるペースに合わせて、次の料理を出すタイミングを調整すべきか。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
【公開問題18】
『お客様の動作から読み取る心理的サイン』
接客業においては、お客様の言葉だけでなく、表情や動作から心理状態を読み取ることも大切です。たとえば、お客様が急にキョロキョロと周囲を見渡し始めた場合、それは何らかの不安や要望のサインである可能性があります。このような非言語的なサインに気づき、適切なタイミングで声をかけることが、顧客満足度の向上につながります。スタッフは日々の業務の中でこうした観察力と対応力を磨いていくことが求められます。[問 題]
お客様が、お席でキョロキョロ周りを見渡し始めました。この場合のお客様心理として可能性があるものを(ア)~(オ)の中から全て選びなさい。
(ア)お箸(フォーク)等を落としてしまったため、店員を呼ぼうとしている。(イ)注文した商品がなかなか提供されず、いつ来るのかが不安で回りを見渡した。
(ウ)お手洗いに行きたくなり、トイレを探しはじめた。
(エ)提供された料理を食べていたところ、味に違和感があり、店員を呼ぼうとしている。
(オ)注文内容が決まったので、店員を呼ぼうとしている。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
【公開問題19】
『会計時の応対』
お客様がお店を評価する心理には「ピーク・エンドの法則」があり、最も印象的な場面(ピーク)と体験の最後(エンド)が記憶に残りやすいとされています。飲食店では、お会計がその「エンド」にあたることが多く、この瞬間の接客対応が、店全体の印象を左右すると言っても過言ではありません。[問 題]
お会計時でのお客様との対応について、次の(ア)~(オ)の中で、不適切なものを1つ選びなさい。
(ア)お会計の金額を伝える際には「合計〇〇円でございます。」と、はっきりと丁寧な言葉遣いを心がけましょう。また、お客様が注文された内容を簡単に復唱しながら金額を伝えることで、お客様も安心して確認できます。(イ)お客様がどのように支払いたいか、まず確認しましょう。例えば、「お支払い方法は、いかがなさいますか?」と尋ね、現金、クレジットカード、QRコード決済など、利用可能な方法を伝えます。キャッシュレス決済の場合には、決済端末への誘導や操作の案内をスムーズに行い、お客様が迷わないようにサポートしましょう。
(ウ)お客様の決済が完了したことを、口頭とレシートで明確に伝えましょう。「〇〇円、お支払いが完了いたしました。」や「決済が完了いたしました。」と伝え、同時にレシートをお渡しします。これにより、お客様は支払いが無事に終わったことを確認でき、安心感が得られます。
(エ)領収書が必要なお客様には、宛名は確認せずに、常に宛名なしで発行します。発行する際には「こちらをどうぞ」とだけ一言添えて、内容については再確認する必要は一切ありません。
(オ)お会計が終わり、お客様が店を出る際には、「ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。」と心を込めて伝え、丁寧にお見送りしましょう。この最後の瞬間が、お客様に良い印象を残し、次回の来店へと繋がります。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
【公開問題20】
『インボイス制度』
2023年10月から始まったインボイス制度は、正確な消費税の申告と控除のために必要な仕組みです。 飲食店も適格請求書発行事業者として登録し、領収書の発行時には一定の記載事項が求められます。正しい記載がなければ、取引先が仕入税額控除を受けられず、信頼や取引に影響を及ぼす可能性があります。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中で、領収書発行の際にインボイス制度に即した記載事項として不要なものを1つ選びなさい。
(ア)インボイス発行事業者の名称と登録番号(Tから始まる13桁)(イ)取引年月日
(ウ)税率ごとに区分して合計した販売額
(エ)印鑑
(オ)税率ごとの消費税額または適用税率
出典:国税庁_インボイス制度の概要(インボイス制度って? → インボイス制度の記載事項について)
【公開問題21】
『決済知識/QRコード決済』
2024年のキャッシュレス決済比率は42.8%まで上昇しており、中でもQRコード決済の利用は9.6%(13.5兆円)を占めています。 キャッシュレスの利便性が高まる一方で、店舗側も決済の仕組みや税の取り扱いについて正しい知識を持っていなければ、会計ミスやトラブルに繋がります。特に消費税率の違いやレシート処理には注意が必要です。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中から、QRコード決済に関する正しい知識として間違えているものを1つ選びなさい。
(ア)QRコード決済はキャッシュレス決済の一種である。(イ)QRコード決済の利用比率は年々上昇している。
(ウ)QRコード決済を利用した場合、消費税は8%である。
(エ)レジ設定によりQRコード決済と連動した領収書の発行が可能である。
(オ)キャッシュレス決済導入は飲食店の業務効率化に貢献する。
出典:NEC_QRコード決済とは?仕組みや種類、メリット・デメリットまで詳しく解説
出典:PayPay_飲食店経営者なら知っておきたい軽減税率の基本事項と売り上げアップのコツ
【公開問題22】
『クレーム対応』
飲食店でのクレーム対応は、お客様の信頼回復のチャンスであり、サービス改善の重要な情報源です。誤った対応をすると、トラブルが大きくなることや悪評が広がる可能性もあります。一方で、適切な対応を行えば、逆に顧客満足度が高まり、リピーターにつながることもあり、基本的なクレーム対応の手順と心構えを理解することが重要です。[問 題]
飲食店でクレーム対応をする際の基本対応を手順に沿って(ア)~(オ)に記載しました。(ア)~(オ)の中で、不適切なものをひとつ選びなさい。
(ア)クレーム内容をしっかりと聞きます。お客様の話は最後まで遮らずに聞くことが大切です。何が原因で、どんな気持ちでいるのかを把握し、反論せず傾聴する姿勢を示しましょう。(イ)お客様からの不満や苦情に対しては、まずは言い訳をします。表情や態度、言葉遣いなどには気を使いながらも、お店の立場からの意見を伝えます。
(ウ)相手の立場に立って謝罪します。お店に非がある場合はもちろん、お客様の誤解であっても「不快な思いをさせてしまった」ことには謝罪します。ただし、全面的な謝罪は避け、非のある部分を明確に謝罪しましょう。困ったら責任者に報告してください。
(エ)問題が分かったら、速やかに解決に向けて対応します。お客様の状況も考慮し、柔軟に対応しましょう。解決後も責任者への報告は忘れずに行います。
(オ)お客様の怒りが収まらない場合は、責任者に交代することも検討します。お客様の了解を得て、責任者にはこれまでの経緯を簡潔に伝え、お客様に同じ話を繰り返させないよう配慮しましょう。
出典:過去S1サーバーグランプリお客様評価より抜粋問題
参考資料:店舗改善ラボ
【公開問題23】
『マーク問題』
厚生労働省の調査によると、我が国における障害者数の概数は、身体障害者(身体障害児を含む)で約436万人とされています。日常生活や移動に支援を必要とする方々が安心して社会参加できるよう、各種マークが整備されており、これらのマークを正しく理解することは、店舗スタッフとして重要な配慮の一つです。マークが意味する状況や支援の必要性を知っておくことで、スムーズかつ適切な接客・支援が可能になります。[問 題]
下記のマークに関する説明として正しいものには〇を、誤っているものには×をつけなさい。
 (ア)【ベビーカーマーク】
(ア)【ベビーカーマーク】→ ベビーカーを使用する保護者を優先的に案内・配慮する必要があることを示すマークで、鉄道駅や商業施設などに掲示されている。
(イ)【ハート・プラスマーク】
→ 内部障害や内臓疾患など、外見からはわかりにくい障害を持つ人が支援を必要としていることを示すマークである。
(ウ)【耳マーク】
→ 聴覚障害があることを示すマークであり、筆談やゆっくりした話し方などの配慮が求められる。
(エ)【授乳マーク】
→ 授乳やおむつ替えができるスペースを示すマークであり、主に商業施設や公共施設で使用されている。
(オ)【ほじょ犬マーク】
→ 身体障害者補助犬法に基づき、盲導犬・介助犬・聴導犬が同伴可能であることを示すマークである。
出典:福祉局
出典:全日本難聴者・中途失調者団体連合会
出典:厚生労働省身体障碍者補助犬
出典:子供家庭庁すこやか親子21
出典:国土交通省バリアフリーユニバーサルデザイン
【公開問題24】
『緊急時の対応/地震』
2024年の1年間で「震度4以上」の地震は113回(前年は41回)と、地震の発生頻度が増加しています。 飲食店では、お客様や従業員の命を守るためにも、日頃から地震発生時の初動対応について知識を身につけ、行動の訓練を行うことが重要です。冷静な判断と行動が事故や被害を最小限にとどめます。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中から、地震発生時の初期対応として間違えているものを1つ選びなさい。
⓵地震だ!まず身の安全揺れを感じる、緊急地震速報を受けた時は、[(ア):身の安全 ]を最優先に行動する。 丈夫なテーブルの下や、物が「落ちてこない」「倒れてこない」「移動してこない」空間に身を寄せ、揺れがおさまるまで様子を見る。 ⓶落ちついて 火の元確認 初期消火
火を使っている時は、揺れがおさまってから、[(イ)あわてず] に火の始末をする。出火した時は、落ちついて[(ウ)消火する。]
⓷あわてた行動 けがのもと
屋内で転倒・落下した家具類やガラスの破片などに注意する。瓦、窓ガラス、看板などが落ちてくるので[(エ)外に飛び出すときは頭上に気を付ける。
⓸窓や戸を開け 出口を確保
揺れがおさまった時に、避難ができるよう[(オ)出口]を確保する。
出典:東京消防庁_地震だ! まず身の安全
【公開問題25】
『緊急時の対応/火災』
2024年に発生した飲食店火災は全国で554件と、一日一件以上の頻度で発生しています。 火災が起きた際には初期対応が重要であり、従業員が適切な行動を取ることでお客様の命を守ることができます。火災時の行動を事前に確認し、いざというときに備えておくことが必要です。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中で、飲食店で火災が発生した際の対応として間違えているものを1つ選びなさい。
(ア)火災時は周囲に大きな声で助けを求める。(イ)初期段階では消火器を使用して消火を試みる。
(ウ)火が天井に広がった場合は110番に通報して助けを求める。
(エ)近隣住民と連携して子どもや高齢者の避難を優先する。
(オ)バケツリレーなど安全が確保されていれば延焼防止を試みる。
出典:消防庁_防災マニュアル 5.救出・救護・初期消火
【公開問題26】
『接遇マナー/テーブルマナーの基本』
飲食店のスタッフは、料理を提供する立場として、和食・洋食・中華それぞれのテーブルマナーについて基礎的な知識を持っておくことが求められます。お客様の食事をより快適にするためには、文化や料理に合ったマナーを理解し、間違った助言や対応を避けることが重要です。とくに宴席や接待の場面では、マナーの知識が信頼を生む要因にもなります。[問 題]
次の(ア)~(カ)の中で、テーブルマナーとして不適切なものを選びなさい。
(ア)和食では、食べる前にお椀にふたがついている場合は、ふたを外して裏返しにしておき、食べ終えたら元に戻す。(イ)フランス料理でナイフやフォークがたくさん並べられている場合は、外側から順に使う。ナイフやフォークを食事中にいったん置く場合は、ナイフは刃を手前に向け、フォークは背が上になるようにして皿の上に「八の字」にしておく。食事が終わったら、ナイフとフォークの柄が右斜め下に向くように揃え、皿の上に置く。
(ウ)フランス料理では、ナプキンは二つ折りにして、折り目がお腹側にくるようにして膝の上に置く。食事中に席を立つときは、軽くたたんで椅子の座面か背もたれに置く。食事が終わったらあえてざっくりとたたみ、テーブルの上に置く。
(エ)中華料理では、料理はまず主賓や年長者が取り、自分の分の料理を取ったら次の人のために回転台を「時計回り」に回す。食べ始めるのも、主賓や年長者が箸をつけてから食べる。
(オ)中華料理では、料理を食べる際、取り皿を手に持ち、麺類はれんげ等は使用しない。料理ごとに取り皿を変えないのが正式なマナー。
出典:求人飲食店ドットコム_飲食店スタッフなら知っておきたい!!最低限のテーブルマナー
【公開問題27】
『コンプライアンス/個人情報保護』
『個人情報保護法』では、特定の個人を識別できる情報(氏名、住所、生年月日、顔写真など)を「個人情報」と定義しています。 飲食業界ではコロナ禍でDX化が促進したこともあり、予約やモバイルオーダーの活用、売上分析などの際に、個人情報を取り扱う機会も増えてきています。お店によっては、会員制度などにより、お客様の「個人情報」を多くの従業員が管理する事があるかと思います。[問 題]
以下の(ア)~(オ)のうち、個人情報の取扱いとして不適切なものをすべて選びなさい。
(ア)来店されたお客様が好みのタイプだったので、会員制度登録で入手したお客様の電話番号に、自分の携帯電話から連絡した。(イ)来店されたお客様が芸能人だったので、その名前を含めて自身のSNSに投稿した。
(ウ)お客様の顔がはっきり写っている満席の店内写真を、承諾なしに投稿した。
(エ)お店で得た会員情報を、自宅のパソコンに移して個人で保管した。
(オ)転職の際、前職の顧客情報を新しい職場に共有した。
出典:政府広報オンライン 「個人情報保護法」を分かりやすく解説。個人情報の取扱いルールとは?
出典参考:JFEX_飲食店のSNS活用6つのポイントと注意点を解説!SNS集客の成功事例も紹介(飲食店のSNS運用における注意点とリスク管理)
【公開問題28】
『リスク管理/SNS活用の注意点』
SNSは集客に役立つ反面、発信の内容次第では炎上や信頼失墜のリスクを伴います。正しい運用ルールを知っておくことが大切です。[問 題]
次の(ア)~(オ)のうち、間違っているものを1つ選びなさい。
(ア)店舗の公式アカウントは、投稿前に内容をチェックし、不適切な表現がないか確認する。(イ)従業員の個人アカウントでも、店舗の内部情報の投稿は避けるべきである。
(ウ)SNSでクレームが拡散された場合は、事実確認をせずに即座に反論するのが望ましい。
(エ)定期的にSNS運用の見直しを行うことで、炎上リスクを軽減できる。
(オ)お客様からの問い合わせには、誠実かつ迅速に対応し、信頼関係を築く。
出典参考:JFEX_飲食店のSNS活用6つのポイントと注意点を解説!SNS集客の成功事例も紹介(飲食店のSNS運用における注意点とリスク管理)
【公開問題29】
『衛生管理/持ち帰り食品の注意点』
飲食店では、持ち帰り食品の衛生管理も重要な課題です。不適切な取扱いは食中毒のリスクを高めてしまいます。[問 題]
以下の(ア)~(オ)のうち、誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)持ち帰り用の食品は、適切な温度管理を行い、食中毒のリスクを軽減する。(イ)持ち帰り用の食品は、提供後すぐに食べることが推奨される。
(ウ)持ち帰り用の食品は、常温で長時間放置しても安全である。
(エ)持ち帰り用の容器は、衛生的な素材を使用し、食品の品質を保つ。
(オ)持ち帰りの際には、消費期限や保存方法を明記することが望ましい。
出典:厚生労働省_食品ロスの現状と食べ残しの持ち帰りについて(22ページ)
【公開問題30】
『洗浄・消毒の基本』
消毒によって、器具に付着した菌やウイルスを無力化することができます。洗浄だけではすべての菌やウイルスを洗い流すことは難しいため、残った菌・ウイルスを消毒作業で退治する必要があります。 また、「殺菌」「滅菌」「除菌」「抗菌」など、似たような言葉もありますが、それぞれ意味が異なります。 器具を洗浄・消毒する際は、必ず「洗浄」→「消毒」の順番で行うことが重要です。汚れがある状態で消毒をしても、菌に薬剤などが届かず、生き残ってしまいます。 必ず、先に「洗浄」で汚れを落とし、続いて「消毒」で残った菌・ウイルスを死滅させましょう。[問 題]
以下の(ア)~(オ)のうち、「消毒」に関する記述をしているものを1つ選びなさい。
(ア)食中毒菌や病原性ウイルスを死滅させる、感染力をなくす、害のない程度まで減らす等の方法で感染のリスクをなくす(=無毒化する)こと。(イ)病原性の有無にかかわらず、すべての微生物を死滅させること。定義としては、微生物の生存する確率が100万分の1以下になること。
(ウ)病原性の菌やウイルスを死滅させること。どれくらい死滅させるかの定義はない。
(エ)増殖可能な菌を除去、減少させること。減少させる菌数や割合は決まっていない。
(オ)菌の増殖を抑制したり、感染力を弱めたりすること。菌を死滅させたり、除去したりするわけではなく、また、どれくらいの増殖を妨げればよいかなどの基準もない。
出典:容器スタイルマガジン_飲食店における正しい洗浄・消毒の方法とHACCP導入による作業の標準化
【公開問題31】
『商品知識』
飲食店のスタッフは、お客様に提供する食材について正確な知識を持っていることが求められます。とくに牛肉は部位によって食感や風味、調理法の適性が異なるため、基本的な部位ごとの違いを把握していると、自信を持って提案や説明ができ、信頼を得ることにもつながります。[問 題]
牛肉の部位に関して、以下の(ア)~(オ)のうち、間違えているものを1つ選びなさい。
(ア)ヒレ肉は脂肪が少なく、柔らかい部位である。(イ)リブロースは霜降りが多く、ステーキやローストに適している。
(ウ)肩ロースは赤身が多く、煮込み料理に向いている。
(エ)サーロインは運動量が多いため、硬くて煮込み向きの部位である。
(オ)バラ肉は脂肪が多く、焼肉やカルビに適している。
出典:島根県食肉事業協同組合連合会「牛肉の部位と特徴」
【公開問題32】
『季節の食事系』
飲食店で提供する料理には、旬の食材を使うことで季節感を演出し、料理の魅力を高めることができます。旬の食材は栄養価が高く、風味も良いため、顧客満足度にもつながります。スタッフが旬についての知識を持っておくことで、接客時の会話やおすすめの際に役立ちます。以下の選択肢から、旬の食材に関する誤った説明を選んでください。[問 題]
下記の(ア)~(オ)の中から、旬の食材に関する情報として不適切なものを1つ選びなさい。
(ア)旬とは自然の中でふつうに育てた野菜や果物がとれる季節や、魚がたくさんとれる季節のことで、食べ物によってその時期は異なる。(イ)春の旬の食べ物は、菜の花、イチゴ、アサリ、タケノコなどである。
(ウ)夏の旬の食べ物は、キュウリ、トマト、アジ、スイカなどである。
(エ)秋の旬の食べ物は、サツマイモ、柿、サンマ、栗などである。
(オ)冬の旬の食べ物は、トマト、キュウリ、アスパラガスなどである。
出典:農林水産省「子どもの食育」
【公開問題33】
『乳幼児の食事と安全』
子どもに提供する食事では、成長段階に応じた食材の選び方や調理法に注意が必要です。とくに幼児期は、咀嚼力や飲み込む力が未熟であるため、食品による窒息事故が多く報告されています。安全に配慮した提供方法を理解し、事故を未然に防ぐ知識が飲食従業員にも求められます。適切な判断が求められる場面も多いため、正しい知識を確認しておきましょう。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中から、幼児に食べさせてはいけない食材として誤っているものを1つ選びなさい。
(ア)ミニトマトやブドウは丸ごとではなく、半分に切って提供する。(イ)もちや白玉団子は弾力が強く、窒息の危険があるため注意が必要。
(ウ)イカやタコは噛み切りにくいため、幼児には避けるべき食材である。
(エ)幼児の食事には、硬いナッツ類をそのまま提供することが推奨される。
(オ)加工食品(ハム・ベーコン)は塩分が多いため、控えめにする。
出典:消費者庁
【公開問題34】
『高齢者食事問題』
高齢化社会が進む現代の飲食店では、シニア層(※)のお客様への対応力が求められています。高齢のお客様の中には、加齢により聴力・視力・筋力などの身体機能が低下している方も多く、店員の何気ない言動が不安や不快感を与えてしまうこともあります。そうしたお客様にも安心して食事を楽しんでいただくためには、接客時の姿勢や話し方、伝え方に対する十分な配慮が重要です。 (※ここでは、60歳代から100歳以上のかたをシニア層とします)[問 題]
次の(ア)~(オ)の中から、シニアに対する接客で心がけた方がよいと思われるものを全て選びなさい。
(ア)シニアに顔を見てもらえる位置に入り、お互いに目線を合わせて話すことができる姿勢をつくる。(イ)シニアは上を向くのが苦手で、上からの目線は高圧的に感じられることがあるため、同じ高さか、やや下から目線を合わせるようにする。
(ウ)加齢で聴力が衰えると高音が聞き取りにくくなるため、声のトーンを落とし気味に話すとよい。
(エ)ゆっくりと抑揚をつけて語尾を強く発音し、相手と同じスピードで話すとよい。
(オ)口の動きをはっきりと見せたり、表情や身振り手振りを大げさにしたりしてオーバーアクションで話すと伝わりやすい。
出典:東芝テック株式会社_シニアに選ばれる店舗と接客
【公開問題35】
『自転車の酒気帯び運転と飲食店の責任』
2024年11月の道路交通法改正により、自転車においても「酒気帯び運転」が新たに罰則の対象となりました。これにより、飲酒の状態で自転車を運転する行為や、それを助長するような酒類の提供も厳しく規制されるようになっています。特に飲食店従業員が、自転車で帰宅予定の客に対し酒類を提供した場合、その責任を問われる可能性があります。安全と法令順守の観点から、飲食店としても最新の法改正内容を理解し、適切な対応が求められます。[問 題]
次の(ア)~(オ)の中から、自転車の「酒気帯び運転」に関わる禁止事項、罰則内容について、適切と思われるものを選びなさい。
(ア)酒気を帯びて自転車を運転することを禁止する。(イ)自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供することを禁止する。
(ウ)酒気帯び運転の罰則は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金である。
(エ)自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供した場合、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合の罰則は、酒類の提供者に2年以下の懲役または30万円以下の罰金である。
(オ)アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自転車を運転する行為は「酒酔い運転」とされ、罰則として5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。
出典:求人飲食店ドットコム「自転車の『酒気帯び運転』に罰則導入。飲食店への影響は?」
【公開問題36.37】
問36と問37はお店における接客サービスのシーンへの論述問題です。各設問を下記の前提条件に従って、100文字以上で論述してください。
(前提条件)あなたは、フルサービスを提供する飲食店のホールサーバーです。
【公開問題36】
[テーマ:個性と表現]
[論述内容]
あなたの接客の武器(特徴)は何ですか。その武器(特徴)をどのように接客に活かしていますか?【公開問題37】
[優先順位]
現在、ご案内できる席(2名席)は一つ空いており、他にお客様が帰ったばかりでまだ片づけられていない席(2名席)が一つあります。ほかの席は満席で30分は空く見込みは無い状況です。この状況において、以下の(ア)~(オ)の事象が同時に発生しました。
(ア)入口にお客様が2名来店しました。
(イ)お客様がお会計を求めています。
(ウ)テーブルのお客様から「すいません」と声がかかりました。
(エ)厨房から料理ができたと声がかかりました。
(オ)片づけていない席のバッシング。

 お問い合わせ
お問い合わせ